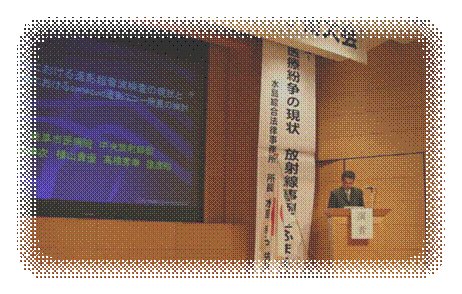 会員発表2
会員発表2
2−1)
当院における造影超音波検査の現状と肝血管腫における
sonazoid造影エコー所見の検討
岐阜市民病院 中央放射線部
○林伸次 横山貴優 高橋秀幸 猿渡裕
〔はじめに〕
第一世代超音波造影剤Levovistが使用されてから8年が過ぎ診断のみならず治療効果判定や治療支援の有用性が認識された。今回、第二世代の超音波造影剤Sonazoidが2007年1月より発売され、当院においても2008年3月13日現在Sonazoid使用造影超音波検査は1005件に達した。今回、当院での使用状況と、特に肝血管腫に対して若干の知見を得たので報告する。
〔使用装置〕
東芝メディカルシステムズ製AplioXVまたはXarioXG
〔使用状況〕
造影超音波検査の件数:週約18件、検査日:月曜午後、木曜午後
造影モード:PS-Low
使用探触子:PUT-375BT・PUT-382BT
使用周波数:送信時1.75MHZ・受信時3.5MHz(amplitude modulation)5MHz(differential contrast harmonic imaging)、MI値0.18〜0.3
Focus point:血管相(病変下縁)、Kupffer相(画面下縁)
フレームレート:10〜15fps、Gain70〜90
〔肝血管腫におけるsonazoid造影エコー所見の検討〕
〔対象・方法〕
対象は、MRIにて診断した肝血管腫16例。年齢:58±13(37〜76)歳、男/女:6/10、腫瘍径:18.3±18.1(6.3〜81.2)mm。Sonazoid(0.015mg/kg)を静注した後、vascular phaseから10分後のKupper phaseまでを経時的に観察した。
〔結果〕
early vascular phase:辺縁結節状または地図状染影15例、均一濃染1例、late vascular phase:辺縁結節状または地図状染影9例、均一濃染7例、Kuppfer phase:辺縁結節状または地図状染影3例、均一濃染6例、周辺肝と同等の染影7例。早期濃染を示した1例は、明らかなA-P shuntを伴っていた。
〔結語〕
vascular phaseでの辺縁結節状または地図状染影とKuppfer phaseまで遷延する染影が血管腫の特徴的造影パターンと思われた。
2−2)
造影超音波検査の現状
木沢記念病院 医療技術部 放射線技術課
北村 香織
【はじめに】
当院では、平成19年1月に超音波造影剤ソナゾイドを採用し、同年3月より造影超音波検査を行っている。検査件数は少なく、造影手技もいまだ模索中ではあるが、導入後一年間で27症例を経験したので報告する。
【使用機剤・条件】
装置 使用装置:ALOKA社製 PROSOUNDα10
 モード:CHE(Contrast
harmonic Echo)
モード:CHE(Contrast
harmonic Echo)
MI値:0.23〜0.8
フォーカス:ターゲットの下方3cm程度
ゲイン:横隔膜・門脈壁のみが表示されるよう設定し、画面が均一になるよう深部STCを調節する。
造影剤 ソナゾイド(第一三共)
投与量 体重1キロあたり0.015ml
撮像 血管相の観察:注入から3分間連続
クッパーイメージ:注入後10分後
【検査の現状】
肝細胞癌の診断16例(診断9件、否定3件、不明4件)
転移性肝癌の存在診断2例
治療効果判定8例(RFA後6件、TAE後1件、RFA+TAE後1件)
造影ガイド下RFA1例
【まとめ】
当院において肝腫瘍の診断はおもに造影CTでおこなわれ、撮影タイミングは特殊な場合を除いて時間固定法である。しかし被検者の生理機能・腫瘤の種類によって最適な撮影時間は異なるので、診断が困難であることが少なくない。比べて造影超音波検査はリアルタイムで腫瘤の血流動態を血管相の極早期から連続で観察することができ、肝細胞癌の診断に有用である。また、クッパーイメージではCTでは検出が困難な小さな腫瘤も欠損像として観察が可能で、転移性肝癌の検索には最も有用であろうと思われる。
2−3)当院における造影超音波検査の現状
JA岐阜厚生連東濃厚生病院放射線科
安藤秀人、大久保久司、今井信輔、松野俊一
【はじめに】超音波造影剤「ソナゾイド」が昨年1月に発売されて以来、当院の造影超音波検査(以下CEUS)の件数は飛躍的に増加した。現在、CEUSは当院の肝癌治療および診断において欠くことの出来ない重要な検査法となっている。今回、当院におけるCEUSの現状とその有用性を報告する。
【CEUS件数】週3〜6件 月約20件 検査日は火曜日午後に設定
【使用造影剤】ソナゾイドのみ
【使用用途】質的診断33%、治療効果判定40%、存在診断23%、治療ガイド6%
【プロトコール】使用超音波診断装置GE社製:LOGIQ9(BT06)、造影モード:CPI(Coded Phase Inversion)モード、MI値:0.17〜0.23、送受信周波数:2MHz/4MHz、フォーカス:1点、フレームレート:14Hz
使用用途によらず、MI値およびフォーカスは観察部位、病変によって最も良い条件を選択する。
【検査の流れ・方法】
1,通常Bモードにて最適走査方法の決定。
2,装置条件(フォーカス、MI値)の設定。
3,観察方法の最終確認(本番前の練習)。
4,CEUS血管相評価
5,必要あれば、再注入にて評価
6,CEUS後期相(15〜20分後)の全肝評価
造影前に時間があれば、ドプラ評価行う。診断に必要な場合のみ、高音圧送信(CHA)を用いて、再還流評価行う。
【再注入法】当院では、最初の注入でターゲットの血管相評価が不可能あるいは困難であった場合に積極的に再注入法を行う。特に局所治療後でターゲットが同定困難な結節に対しての治療効果判定に有用である。
【栄養血管の同定】TACE治療を行う肝細胞癌では、治療前に造影CTにて腫瘍血流の評価が行われており、CEUSでの腫瘍血流の評価を必ずしも必要としない場合が多い。リアルタイムに観察可能なCEUSでは、むしろ治療する栄養血管の描出が期待されると考える。当院では栄養血管の区域枝推定をTACE前に行い、推定可能かどうかを検討している。
 【まとめ】ソナゾイド造影エコー法の使い方によって、目的に応じた明瞭な画像が得られ、当院における肝腫瘍の診断・治療において非常に重要な位置づけとなっている。
【まとめ】ソナゾイド造影エコー法の使い方によって、目的に応じた明瞭な画像が得られ、当院における肝腫瘍の診断・治療において非常に重要な位置づけとなっている。
2−4)
当院の造影超音波検査の現状
大垣市民病院 診療検査科 形態診断室
○ 乙部克彦、竹島賢治、高橋健一、今村啓史、加藤廣正、高木明美、後藤孝司
橋本智子、丹羽文彦、安田英明、橋ノ口由美子、川地俊明
超音波造影剤ソナゾイドが発売されて約1年が経過した。従来の超音波造影剤レボビストと比べその大きな特長は、静注後10分以降の時相(後血管相)の評価が長時間かつ何度も評価できる点にある。特に転移性肝癌(Meta)や肝細胞癌(HCC)などの悪性腫瘍の検出には特に有用である。また血管相の腫瘍の血流評価においてもリアルタイム性が高いことからより細かな血流動態の把握が可能であり、各社より様々なソフトの開発がなされているのが現状である。
当院ではレボビスト使用時から造影超音波検査は肝腫瘍の鑑別診断、HCCの治療効果判定には欠かせないものとなっているが、第二世代の造影剤ソナゾイドの登場によりさらにその幅が広がってきている。肝腫瘍の鑑別診断、HCCの治療効果判定はもちろんのこと、リアルタイム性の高さと後血管相での観察時間の延長と再現性により、造影下でのラジオ波焼灼術(RFA)の治療支援、また後血管相における消化器系癌患者の術前肝転移の有無、慢性肝炎患者のHCCの検出など幅広く利用されている。しかしながら、ソナゾイドの使用経験を重ねるうちにレボビストより扱いにくい点も存在することが分かってきた。大きな問題点として挙げられるのは、低音圧での撮像のため深部病変に対する感度が低く十分な評価ができないという点である。このような症例に対しては、送信周波数を下げ、音圧を上げるなど対処したが、画質の劣化や目的部位まで十分超音波が届かず評価できず、病変の存在深部に対しての評価はレボビストよりは限界があると思われた。当院の使用超音波装置はTOSHIBA社製Aplio XG,XV、ALOKA Prosound α10を用いているが、肝腫瘍の鑑別にはAplio XG、HCCの治療支援にα10、HCCやMetaの検索には3機種を併用している。当日各造影検査について症例をふまえ造影手技の諸条件を報告する。