脊椎からみた日本の歴史
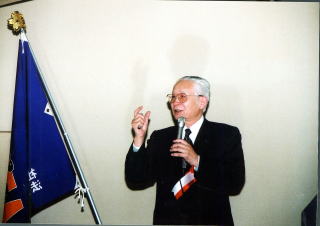 県立多治見病院 臨床顧問 室 捷之
県立多治見病院 臨床顧問 室 捷之
平成15年5月、弥生式土器の放射性炭素測定の新しい検査法によって、それまでの
弥生時代の始まりが500年ほど遡るという説が報告され、世間の話題となった。
我々は、ともすると各時代を年で区分しようとする傾向があるが、人間の歴史がある日突然に変わるわけはなく、徐々に変化していくものであることは当然である。したがって、歴史上の事例を理解するうえには、相当柔軟な思考過程を踏む必要があるといえるであろう。とくに最近の報道媒体では、新知見が出されるとそれらが議論し尽くされて結論が出される前に報道してしまうため、一般の人々が物事の本質を見極めようとしても、先走った報道に惑わされるだけに終始しているのが現状である。
一方では、日頃歴史的常識と思っていることや教えられていることが、極めて根拠薄弱な史料によって巷間に流布している場合も少なくないことは、戦国時代を画くした本能寺の変の前後における明知光秀や羽柴秀吉らの行動を示す新史料の最近の研究が、新事実を明らかにしていることからも良く分かる。今回、人類学者が観察し記録した報告書を見るたびに、遺体を医学的に観察する必要があることを痛感した。
幸い近年になって、古人骨の病的状態を研究する古病理学(paleopathology)が発達してきており、新しい見地からの情報も増加すると思われるが、古病理学の専門家には臨床医師は少なく、忙しい毎日を送る各専門科の臨床医学者が、古病理学者とともに知識を交換しあうことが出来ればと祈念している。
それにしても感心したのは、歴史的なころに関しても、世の中、各専門分野での研究が極限まで追及されていて、普通には知られていない様々なことが解明されているとともに、どの領域でもなお議論が続けられているということで、いわゆる俗説はいうまでもなく、定説ですら何時覆されるか分からないという点を意識すると、先行き不安な現代の社会情勢に相通ずるところがあると思考する今日この頃である。
脊椎日本史の題材探しはなかなか困難で、とにかく沢山の本を読むことが第一であった。墳墓の発掘調査が行われていれば調査報告書を探せばいいが、折角目的の報告書を探し出しても脊椎の画像がないと駄目であり、色々な歴史関係の書籍を読む中で、遺体の存在する可能性があれば、関連の本を探して調べるということになり、これには大変な労力と時間が掛かる。最近ではインターネットが発達してきているので、一見、利用価値が高いと思われるが、実際にはHPの検索でヒットしたことは皆無である。やはり、絶えず書店巡りをして目的に合いそうな本を探し、多くの本を読んで、図書館通いを続けることが、最も役に立つようである。